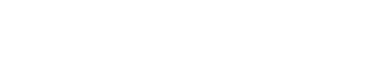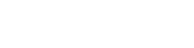天然砥石の実力
砥石には山などで採掘する天然砥石、人の手で人工的に作る人造砥石があります。
1.天然砥石とは
天然砥石の特徴
天然砥石の大きさ
天然砥石の産地
2.天然砥石と人造砥石の違い
切れ味の違い
仕上がりの違い
比較表
3.京都産の天然砥石、東物と西物
東物の大突
西物の大平
1,天然砥石とは
天然砥石とは山や海の地層から産出される砥粒が均一な研磨力のある石です。
天然砥石には荒砥石、中砥石、仕上げ砥石と産地や採掘される山によっておおまかに決められています。
その中でも仕上げ砥石は主に京都産のものが多く、京都産の仕上げ砥石は人や刃物に合わせる砥石という意味から合砥と呼ばれています。
天然砥石の特徴
天然砥石には鋼材の切れ味を最大限引き出すことや見た目を美しく仕上げれるなど様々な特徴があります。
ここではそんな天然砥石の特徴をメリットとデメリットで分けて紹介します。
・鋼材の性能を最大限引き出すことができる。
・刃物の見た目を美しく仕上げることができる。
・砥石が減りにくい
・研げば研ぐほど研ぎ汁の目が細かくなる。
・研いだ刃物が少し錆びにくくなる。
・研いだ刃の硬度が高くなる。
・扱うのに多少技術が必要。
・砥石の性能にあたりはずれがある。
・地を引く可能性がある。
・価格が高い。
天然砥石の大きさ
天然砥石は地層を掘って原石として採掘します。
そのままでは大きい岩の状態なので使用することができません。
そこで割ったり切断したりして使いやすい大きさに加工することで天然砥石の形になります。
天然砥石は何種類か寸法があり、~型と呼ばれることが多いです。
24型 長さ218mm×幅78mm
30型 長さ205mm×幅75mm
40型 長さ205mm×幅75mm
60型 長さ195mm×幅70mm
80型 長さ180mm×幅63mm
100型 長さ160mm×幅58mm
レーザー型 長さ136mm×幅82mm
このように天然砥石はいろいろな寸法があります。また、これらの形を作るときにでた端くれなどの規格外のものをコッパと呼びます。
天然砥石の産地
天然砥石は全国各地から様々な砥石が採れていました。
そのなかでも天然の仕上げ砥石はほとんどが京都から採れたものになります。
また、京都の山の中でも西と東で分かれていて、西の山々を西物、東の山々を東物と呼びます。
ですが今では採掘しているところは残りわずかになり、以前に採れたものが市場に出回っていることがほとんどです。
2.天然の仕上げ砥石と人造の仕上げ砥石の違い
砥石は刃物を削る砥粒または研磨剤と、その砥粒を固めるつなぎまたはボンドで主に構成されています。
砥粒は刃物を削る研磨力に影響し、つなぎは刃物を削る効率性に影響してきます。
天然砥石と人造砥石では砥粒やつなぎの違いから研磨力や硬さが異なるため、切れ味や見た目に違いが出てきます。
切れ味の違い
天然砥石と人造砥石を切れ味の観点から見たとき、
人造砥石に使われている研磨剤はWAなど研磨力の高いものを使用しているため包丁の鋼材にあまり影響されずに研ぎ下すことができます。
その結果包丁の鋼材が違ったとしても似たような切れ味になることがあります。
それに対して天然砥石は砥粒である研磨剤には研磨力があまり高くない天然の石英などが主成分のため包丁の鋼材を研ぎすぎることがなく、鋼材の性能を最大限引き出すことができます。
このように天然砥石と人造砥石では包丁の切れ味に与える影響が変わります。
仕上がりの違い
天然砥石と人造砥石では包丁を研ぎあげたときの見た目の仕上がりが大きく異なります。
人造砥石は均一な研磨力の高さと尖った研磨剤の影響で鏡面のようなピカッとした仕上がりになります。
それに対して天然砥石は研磨力が低く砥粒も鋭すぎないため霞がかった光沢のある仕上がりになります。
仕上げ砥石の比較表
切れ味:鋼材の性能を引き出す
見た目:艶のある曇り
研ぎやすさ:砥石によってバラバラ
砥石の減りにくさ:減りにくいものが多い
価格:比較的高価
切れ味:砥石の性能を引き出す
見た目:鏡面っぽく光る
研ぎやすさ:安定している
砥石の減りにくさ:製法に変化するい
価格:安価なものから高価なものまである
京都産の天然砥石、東物と西物
天然の仕上げ砥石で世界的に品質が良いとされる京都産の天然砥石。
その京都産の天然砥石だけでも京都市の愛宕山を中心に東西に山脈が分かれ、採れる天然砥石の質も少し違い東側で採れる天然砥石を東物、西側で採れる天然砥石を西物と呼んでいます。
東物と西物を比較したとき、東物は硬めの砥石が多く西物は柔らかめの砥石が多い傾向にあります。
包丁を研ぐ場合、包丁は研ぐ面が少しカーブしているため、包丁になじんでくれる柔らかめの砥石のほうが比較的研ぎやすく扱いやすいです。
また、天然砥石は鉋の研ぎにも使用されることが多く、鉋の場合はまっすぐな直線的な刃が好まれるため硬めの天然砥石が適しています。
包丁専門堺實光では東物の大突と西物の大平の天然砥石を扱っています。
東物の大突
大突は東物の天然砥石なので比較的硬めのものが多いです。
特徴としては硬めでとぎ汁もあまり出ないものが多いため研ぐのに多少技術が必要になってきます。
また、柔らかい鋼材や包丁の地金を研ぐ場合、地を引くつまり研いでいるときに砂利のようなものが出てきて傷が入ることがあります。
これは研ぎ方を工夫したりすれば地を引かずに研ぐことが可能なのですが、むやみに研ぐと刃物が傷だらけになる可能性があります。
ですが使いこなせると光沢のある上品な霞仕上げをすることができ、切れ味も滑らかになります。
西物の大平
大平は西物の天然砥石なので比較的柔らかいものが多いです。
特徴としては柔らかめでとぎ汁も出やすいものが多いため天然砥石を初めて使う方にも扱いやすい砥石になります。
大平で研ぎこめばムラも少なく柔らかい霞がかった仕上げになり、切れ味も滑らかになります。
天然砥石についてのよくある質問
ここからは、天然砥石についてのよくある質問にお答えします。
Q: 天然砥石 何番?
A: 天然砥石の番手は、人工砥石のように明確な数値で表すことが難しいとされています。天然砥石は、採掘場所や質により粒子の細かさや研磨力が異なり、番手が明示されていないことが多いです。一般的には、「中砥」や「仕上げ砥」などの分類で使用感が伝えられることが多く、実際の使い心地で自分に合った天然砥石を見つけるのが理想とされています。
Q: 砥石の見極め方は?
A: 砥石の見極め方は、目的や使用頻度、包丁の種類に合わせた選び方がポイントです。まず、自分がどのような仕上がりを求めているかを考えます。日常的なメンテナンスには、#1000〜#3000の中砥石が適しており、切れ味を保ちながら刃の摩耗を防げます。刃こぼれの修正が必要な場合は、#220〜#600の荒砥石を選ぶと効率よく形を整えられます。